
|
一般社団法人 鎌倉同人会が創立100周年祝賀会
市民のお役に立てるよう広がりをもった活動へ |
「歴史的事物及び景勝地保存、衛生の普及、風俗の改良」などを掲げ、史跡保存や住みよい町づくりをめざして大正4年に誕生した鎌倉同人会が、今年の1月で100周年を迎え、3月29日、KKR鎌倉わかみやで祝賀会が開かれた。
本紙では12回にわたって鎌倉同人会が行った事業の数々を紹介してきた。
発起人には、伯爵陸奥広吉(宗光の長男)中心に資力ある有力者が名を列ね、中央とのつながりも深かった。
その業績は、段葛の修復、鎌倉駅改築、郵便局や鎌倉国宝館建設から、関東大震災後の救援、町の清掃などに至る。戦後は主に文化活動を中心に、町にうるおいをもたらしてきた。近代鎌倉を語る上で鎌倉同人会は欠かすことのできない存在。
会場には100数十人が集い、山内静夫第10代理事長は「偉大な先人たちの心を忘れず、新しい発展に向け一歩を」とあいさつ。
貢献者の表彰、松尾鎌倉市長の祝辞と感謝状の授与、そして鏡開きのあと乾杯。フルート奏者吉川久子さんの演奏、そして創設者の子孫も壇上に並び紹介された。
出席者に100周年の感想を聞くと、一様に「びっくりしています。」と答え。では、次の100年への抱負は。
「当時は有力な方が私財を投じ、自ら動き実現させていったが、時代が違う。今は、市民に広く知ってもらい、文化関連事業などで喜んでもらえるような存在となれば。こんないい町はないと思えるように、市民のお役に立てる活動をしていきたい」と山内さん。
同会は創立100周年事業として由比ガ浜海浜公園内に「ここに鎌倉海濱院・鎌倉海浜ホテルありき」の石碑を建立、音楽祭を開催し、また100年史も発行。この100年史は、鎌倉のまちづくりの歴史の一端を知る上でも参考になる。 |
|
2015/4/10 NO188掲載
|
| |

2015/3/10 NO187掲載
|

2015/2/10 NO186掲載
|

2014/12/10 NO185掲載
|

2014/11/10 NO184掲載
|

2014/10/10 NO183掲載
|

2014/09/10 NO182掲載
|

2014/07/10 NO181掲載
|

2014/06/10 NO180掲載
|

2014/05/10 NO179掲載
|

2014/04/10 NO178掲載
|
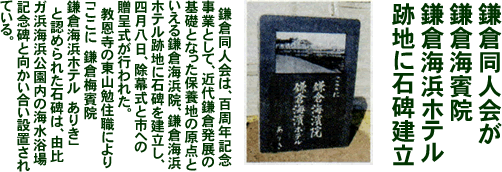 |
| |

2014/0315 NO177掲載
|

2014/0215 NO176掲載
|

2010/1110 NO144掲載
|

2010/0910 NO142掲載
|

2010/05/10 NO139掲載
|
| |
|
|
 |
鎌倉の映画人たち⑫ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
 |
| |
小津安二郎監督と鎌倉
 小津安二郎監督 小津安二郎監督
|
公開されている小津安二郎監督の日記の中の、昭和九年(一九三四年)十月二日に
“早く仕事を上げて鎌倉に転宅したい”
という記述が、前後何の脈絡もなく一行だけ書いてある。深川の生家にいて、蒲田撮影所へ通っていた頃である。三十一歳、漠然とした憧れみたいなものであろう。
昭和二十七年(一九五二年)、大船撮影所の火事がキッカケになって、小津監督は五月二日に鎌倉山ノ内に引っ越し、お母さんと一緒に暮らすことになる。
翌二十八年には「東京物語」を発表、文字通り小津作品の最高傑作であった。面白いことに、この作品以降小津監督は鎌倉を舞台にした映画を一本も作っていない。「晩春」「麦秋」という小津調映画の名作は、何れも鎌倉を舞台にしていたのに、である。つまり、東京を離れてからは逆に東京を舞台にした映画ばかりを撮った。いかにも小津監督らしい反骨精神のような気がする。日常を気楽に過ごす場所を、仕事の場にしたくなかったのかもしれない。確かに、鎌倉に住んでからの小津監督は、リラックスした生活を送られたように思う。北鎌倉の静謐な環境の中での母親との水入らずの時間、着流しで夕方ふらりとまちへ出て気軽に一杯呑む、気を許すことの出来た作家里見弴との深い交遊をはじめ、大佛次郎、今日出海、横山隆一といった人たちとも、気安く行き来できる自由さ、それは映画界の第一人者としての裃を脱いだ人間小津安二郎としての初めての生活だったのではないだろうか。
鎌倉に住んだ十一年八ヶ月、それは六十歳で世を去った小津監督の至福の晩年であった。
晩年と呼ぶには余りにも早く、短かすぎる鎌倉だったと思う。
|
|
NO119
2008/5/10掲載 |
 |
鎌倉の映画人たち⑪ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
|
| |
 岡村さん(左)と田中絹代さん 岡村さん(左)と田中絹代さん
|
岡村文子さん
この欄で、ずっと鎌倉会のメンバーを取り上げてきたが、どうしても忘れてはいけない人がいた。岡村文子さんである。今はもうこの名前を知る人は少いかもしれないが、あの有名な「愛染かつら」で、田中絹代さん演ずるヒロイン高石かつ枝をイビる婦長さん役と言ったら、年配のご婦人方なら、あヽアノ、と思い出される方も多いと思う。昔の映画はそういう脇役に味のある人が多かったので映画が面白かったのだと思う。
大正の初め頃、赤坂ローヤル館のオペラ一座で役者修業、大正十年松竹蒲田に入社。その後一時退社してオペラに戻ったりしたが、最終的に昭和十一年松竹大船に復帰、コメディリリーフとして、又意地悪おばさん役など幅広い役柄で活躍した。田中絹代さんも一目置く古株だから、鎌倉会でも目立つ存在だった。お酒が好きで、ごきげんになると立ち上がってソプラノの喉をご披露した。恋はやさし、花すみれ、カルメンなど、さすが昔とった杵柄で高音も確かで、十分聞き応えがあった。もっとも、メートルが上がりすぎて歌い出すと止まらなくなり、やヽ座がシラけるようなこともあった。肥った丸顔のずんぐりした体型で、にくめない人柄だった。鎌倉在住も古く、一の鳥居脇の、おそらく鎌倉で一番古いマンション〝若宮ハイツ″の住人だった。昭和三十三年(一九五八年)フリーになるまで、大船撮影所では飯田蝶子さん、吉川満子さんと並んで、後輩俳優から先生と呼ばれる存在だった。明治三十一年(一八九八年)生まれ、昭和五十一年二九七六年)七十八歳で亡くなった。
|
NO118
2008/4/10掲載 |
 |
鎌倉の映画人たち⑩ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
|
| |
三井弘次さん
根っからの役者である。三井弘次、戦前は三井秀男という芸名で、松竹映画の作品記録によれば、昭和七年三月の「初恋と与太者」(野村浩将監督)のキャストに初めて名前がのっている。松竹得意の軽喜劇だが、磯野秋雄、阿部正三郎とトリオを組んで、与太者シリーズとして売り出した。年に三本から四本、このシリーズで活躍するうちに、清水宏、小津安二郎といった名監督の眼に止まるようになる。特に昭和九年の小津監督の「浮草物語」は、俳優としての成長を示した。
戦後昭和二十三年、芸名を弘次に改名、名脇役として、他社からも引っ張り凧の活躍だった。昭和三十二年には、渋谷実監督の「気違い部落」や黒澤明監督「どん底」などで、毎日コンクールやブルーリボン賞の男優助演者賞に輝いた。晩年は、持ち味というか、巧まざる技巧というか、地のままでいるようで役の個性を見事に浮き彫りにしていた。天才肌の俳優と言っていい。
大船の所謂松竹通りの中程に住んでおられた。撮影のない日など、通りかかると小さいお嬢ちゃんの手を引いて、庭先に立っているのをよく見かけた。どこにでもいるお父さんのようであった。唯、三井さんの一番の欠点は、酒が入ると止まらないことであった。晩年、撮影にもホロ酔いでやって来たりすることもあったが、セットに入ってライトが当たると、さすがに名優の顔に戻った。勿論、鎌倉会などで、羽目をはずすようなことは一度もなかったが。昭和五十四年没、何故か懐かしい人である。
|
NO117
2008/3/10掲載 |
| |
鎌倉の映画人たち⑨ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
 |
| |
川喜多長政・かしこ ご夫妻
我々が、国内で外国の映画を楽しめるようになったのは、間違いなくこのご夫妻の功績に他ならない。長政氏が外国映画の輸入事業を志し、東和商事を設立したのは昭和三年(一九二八年)である。特にアメリカ映画が主流である日本の市場で、フランス、ドイツ、英国などの芸術性の高いヨーロッパ映画は映画そのものへの関心を高めてくれたものだ。「にんじん」、「望郷」、「どん底」などの戦前作品から、戦後の「第三の男」、「天井桟敷の人々」、「禁じられた遊び」、数え上げればキリがない名作の数々は、生涯忘れられない映画の感動というものを日本人のなかに残してくれた。かしこ夫人は、東和商事設立の翌年長政氏と結婚、以来二人は手を携えてヨーロッパ各地を廻り、これと思う作品を買い付けては日本に送り込んだ。この夫妻の業績は、とてもこの欄のスペースでは描きようもないが、一言で言うならば、真の国際人、映画の枠を超えた世界に通用する日本人であろう。
ご夫妻は、終生鎌倉に居を定めておられた。平成五年かしこ夫人が世を去られた後(長政氏は昭和五十六年逝去)その旧宅は鎌倉市に寄贈され、現在その地に記念館を設立する計画が漸く実現に向かっている。
格調の高いスーツと美しい銀髪の一分の隙のないジェントルマン、昔ながらの髪型と独特の和服姿を変えようとしなかった上品な淑女、その頃よくお見かけした、鎌倉駅で電車を待つお二人の端然とした姿は、まさに鎌倉人士の典型であり、今でも私の脳裏を離れない。
|
NO116
2008/2/10掲載 |
|
鎌倉の映画人たち⑧ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
|
| |

歌舞伎の名脇役
中村嘉葎雄・市川小太夫
渋味と軽みのある独自の芸風である。昭和30年、高校二年の時映画界へ、兄は大スターとなった萬屋錦之助だが、兄弟でも色合いは正反対で、地道な演技派だ。名門中村屋の異端児だが、さすが血筋は争えず、昭和40年代には脇役として引っ張り凧の活躍で、「湖の琴」「わが恋わが歌」「陽炎座」「ブリキの勲章」等で、各種映画コンクールの助演男優賞を総ナメにしていた。
 家が近かったせいもあり、かなり親しく付き合った。仕事に入っている間は、人が変わったように役になりきってしまう。お酒が大好物で、度が過ぎるのが欠点だが、体が空くと、陶芸に打ち込んで伊豆の窯場に籠もりきって、玄人はだしの作品を造る。今は北鎌倉の浄智寺奥に住んでいるが、暫く会っていない。親父が中村歌六という名優で、私の父もその芸が好きだったようで、父の家へ行ってはその昔話を聞くのが何より嬉しかったようだ。役者、という呼び名がピッタリの人だ。 家が近かったせいもあり、かなり親しく付き合った。仕事に入っている間は、人が変わったように役になりきってしまう。お酒が大好物で、度が過ぎるのが欠点だが、体が空くと、陶芸に打ち込んで伊豆の窯場に籠もりきって、玄人はだしの作品を造る。今は北鎌倉の浄智寺奥に住んでいるが、暫く会っていない。親父が中村歌六という名優で、私の父もその芸が好きだったようで、父の家へ行ってはその昔話を聞くのが何より嬉しかったようだ。役者、という呼び名がピッタリの人だ。
もう一人、こちらも歌舞伎界の異端児、先代猿之助の弟、市川小太夫さんが和田塚の近くに住んでいて、松竹映画にチョイチョイ出演していた。風格のある、厳格な父親役などがピッタリだった。日舞で琴吹流という流派を立て、その家元でもあった。素顔は柔和な、気やすい人だったが、昭和五十一年、七十四歳で亡くなった。おふたり共、鎌倉会の常連だった。いまは懐かしい。
|
NO115
2007/12/10掲載
|
| |
鎌倉の映画人たち⑦ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
|
| |
田中絹代さん
 |
笑顔の田中さん、中央は菅原通済さん。
その左、小津さん。後ろは佐田啓二さん |
百年を越す日本映画史の中で、文句なしの大女優と呼べる人は、田中絹代さんをおいて他にはない。失礼ながら、華やかで美しい大スターはあまたいるであろうが、果して大女優と呼べるかどうか。田中さんには、長い女優人生を通して、一貫して映画女優としての矜持を持ち、その頂点に立ち続けた強靱な精神の高さがあった。
戦後間もない大船撮影所は、すべての俳優は専属で毎日のように撮影所に顔を見せていたが、田中さんが姿を見せると、アッと言う間に田中さんを囲んで大きな人の輪が出来た。にこやかな笑顔で誰とでも言葉を交わす田中さんの小さな体からは、まさにオーラを発しているようだったことを、入社当時の私は鮮明に覚えている。
小津作品の撮影の時でも、鎌倉会のような席でも、田中さんはいつも礼儀正しく、私たちのような若輩にも接して下さった。昭和五十年、山根成之監督の「おれの行く道」という作品で、私は人気歌手西城秀樹の主演作品に田中さんの出演をお願いした。田中さんは何もおっしゃらずお引きうけ下さった。有難かったが、慚愧の念にかられた。そして旨が熱くなった。
鎌倉のまちで、素顔にサングラスをかけて買い物をしている田中さんと時々お会いすることがあった。かつてのオーラを放っていた田中さんとは別の、超然と生きる女性としての輝きがあった。
|
NO114
2007/11/10掲載
|
| |
鎌倉の映画人たち⑥ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
 |
| |
津村秀夫さん
 |
中村登監督(左)、シナリオライターの
沢村勉
(右)と談笑する
津村秀雄氏(鎌倉会にて) |
戦前から、朝日新聞の映画批評で“Q”氏と言えば、映画会社は勿論、監督、シナリオライター、俳優まで、一目も二目も置いた怖い批評家である。映画批評というものが、評論の一分野として確立されたのは、このQ氏の存在が大きかった。
一九〇七年(明治四〇年)神戸の生まれ、東北帝大独文卒、朝日新聞入社、一九三二年(昭和七年)から映画批評欄を担当する。歯に衣を着せぬ痛烈な文章で、ズバリと映画の良否を示した。昭和十三年、松竹の「愛染かつら」が空前の大ヒットとなったが、Q氏はこれを「一見に値する愚作」と切り捨てた。Q氏が取り上げたというだけで、作品の格が上がるとさえ言われた。
鎌倉住まいも永く、前にも書いた鎌倉会もQ氏が音頭をとって、川喜多夫妻や小津安二郎、田中絹代に呼びかけたもので、さしずめ幹事長と言った中心的な存在だった。いかにも大人といった風格であった。若い頃は作家志望であったらしく同人誌に加わっていたこともある。なお実弟の津村信夫は、作家詩人として名を成し、同じ鎌倉の在住していた。
映画全盛時代で、新聞各紙とも映画評に力を入れていたが、中でも朝毎読の三大紙は、この朝日のQ氏、毎日はO氏岡本博、読売はタニキンも愛称で親しまれた谷村錦一氏といった名物記者がいたことも懐かしい。一九八五年(昭和六0年)没。
|
NO113
2007/10/10掲載 |
| |
鎌倉の映画人たち⑤ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
|
| |
 |
カルメン故郷へ帰るのスチール
写真の前でスタッフと、
(背景写真の左が井川さん) |
井川邦子さん
鎌倉駅を出て、まっ直ぐ若宮大路を越し、通称おんめさまという大巧寺の脇の小径を小町大路へ抜けたすぐ右側「珈琲 井川」という看板が眼に入る。もう三十年以上、落ち着いたムードで、コーヒーの味を愉しめる店として、地元のファンの多い店だ。ここが、戦後から昭和三十年代の中頃まで、松竹大船のスターとして活躍した井川邦子さんのお店である。昭和二十一年、戦後早くも頭角を現した木下恵介監督の「わが恋せし乙女」で主役に抜擢され、以後「結婚」「肖像」「カルメン故郷に帰る」など、木下作品に次々と出演、世に謂う“木下学校”の優等生としてスターの道を歩んだ。
人の運とは不思議なものだ。彼女は昭和十五年から松竹に入り、河野敏子の芸名でデビューしたが、戦時中でもあり、仲々メが出なかったが、戦後、井川邦子に改名してから一気に花開いた。眼の大きい、明るい美人で、その上、品の良さと淑やかさが、松竹映画のカラーにマッチして、誰からも好かれる女優さんだった。小津作品には「お茶漬けの味」に出演した。大船撮影所が最も華やかな女優王国と呼ばれた時代の中で、木下学校という色が、出演作品の幅を狭めたことがあったかもしれない。昭和三十五年、木下作品の「笛吹川」を最後に、映画界を去った。
その後、鎌倉会などにもよく顔を見せられていて、相変わらぬ美しさだった。
近頃は、お店に行ってもお顔を見ることが少ないとのことだが、まだまだお元気でいていただきたい鎌倉の映画人のひとりだ。
|
NO112
2007/9/10掲載 |
| |
鎌倉の映画人たち④ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
|
| |
シナリオライター 野田高梧
日本のシナリオライターの中で、まぎれもなく大御所的な存在であった。早稲田大学を出て、一九二四年(大正十三年)、松竹蒲田撮影所の脚本部に入った。映画における脚本の重要性が、認められ出した頃だ。同時に、映画の題材が日常の生活感情の機微を描くようになる、所謂松竹調の小市民映画の分野を切り拓いた功績は大きい。戦後の小津安二郎監督作品、「晩春」以降の全作品のシナリオを、小津監督と共同で執筆したことで知られる。小津作品独特のユーモアとペーソスは、野田さんの持味とも言える。
飄飄として、やわらかな人柄で、酒を愛し、興至れば、「伊那の勘太郎」の歌謡曲の当て振りを気軽に踊ったりした。後輩の若いシナリオライター連中にとっても、煙たくない、親しまれる先輩だった。小津作品の数々が代表作であることは間違いないが、戦前の作品で記録的な興行成績をあげたメロドラマ「愛染かつら」も氏の作品であることも特筆に値する。
その著書「シナリオ方法論」「シナリオ構造論」は、シナリオを志す人たちのための永遠のバイブルと言える名著だ。
戦後、シナリオ作家協会の初代会長となったが(昭和25年)、面白いのは日本で初めてという大船撮影所の従業員組合の最初の委員長も勤めた。日本映画界の、巨人のひとりと言えよう。
盟友ともいえる小津安二郎の死(昭38)から五年後(昭43)、世を去った。(享年75歳) |
NO111
2007/7/10掲載 |
| |
鎌倉の映画人たち③ 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
|
| |
宇佐美淳さん
 |
鎌倉会の宴席で談笑する宇佐美淳さん
左となり堺駿二さん 奥は筆者
愉しそうな雰囲気が伝わってくる |
一昔前には、ハイカラ、ということばがあった。宇佐美淳さんは、まさにそれである。ちょっと日本人離れした彫りの深い顔立ちの二枚目だった。戦前は、新興キネマのトップスターで、戦後すぐから松竹に移った。上原謙や佐分利信と同世代だが、松竹育ちのスターたちとは一味違う、おしゃれな感じがあった。
鎌倉へ来られたのも、戦後すぐではないだろうか。佐助の、御成中へあがる道の角の大きな門構えの家であった。昭和二十四年の小津作品「晩春」に出演されたので、知り合った。気さくな明るい人だった。時々、朝早くわが家の玄関で、お早うございます、と大声がするので出てみると、宇佐美さんが愛犬のシェパードを連れて、ニコニコ顔で立っている。「何かお仕事はありませんか」とジョークを言ったりする、そんな人だった。でも、本音はきまじめで静かな人だったのではないか、そんな気がする。
宇佐美さんの二人のお嬢さん、姉はオペラ歌手の宇佐美瑠璃さん、妹はピアニストの駒木佐地子さん、先日このお二人のジョイントコンサートがあった。佐地子さんのひとり娘宏美さんも司会をつとめ、一家水入らずの心温まる一夕だった。
宇佐美さんのやさしい笑顔と眼差しが、頭をよぎった。
|
NO110
2007/6/10掲載 |
| |
鎌倉の映画人たち② 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
 |
| |
笠 智衆さん
笠さんは、お酒を呑まない。若い頃は大いに呑んだ、という話を聞いたような気もするのだが、少しアヤフヤだ。
だから、宴会などでは一向に目立たない。鎌倉会でも、お酒が廻ってワイワイガヤガヤになっても、笠さんは唯ニコニコしている。座の中心は、何と言っても小津安二郎監督だ。一しきり座談がはずんだ後は、必ずといってよい程小津監督から声がかかる。
「笠さん、あれやってくれや、あれ」
笠さんは、小津監督のことばは断れない。小津監督のリクエストは、「のぞきからくり」である。やおら正座すると笠さんは、真面目くさって、湯飲茶碗片手に箸でそれを叩き合いの手を入れながら歌う。
チャンチヤチャンチャン
三府の一の東京で
ハァドッコイ
波に漂うますらおが
果てなき恋にさまよいし
ハァドッコイ
新派悲劇〝不如帰(ほととぎす)″である。声といい節回しといい、絶品である。シーンとしずまりかえってしまう。
笠さんの隠し芸は、これだけではない。詩吟、軍歌、どれも聴きほれる。みんな小津映画の中でやったものだが、その度に笠さんは、余程練習を重ねたに違いない。
律儀な笠さんのことだから、小津監督から言われたら、宴会でも撮影の時と同じように緊張したのではないかと思うと、可笑しくも懐かしい
|
|
| |
鎌倉の映画人たち① 山内静夫(鎌倉文学館館長) |
|
| |
小津安二郎の日記
一九五三年 昭和二十八年一月三日(土) 略。
鎌倉会の発会式が長谷の華正桜であるので出かける。大変な人出だ 駅から車でゆく
出席者
川喜多長政 同かしこ
絹代 笠
岡村 三井 宇佐美
高梧 勉
月丘千秋 市川小太夫
井川 岩間
津村秀夫 同弥生 青木富夫
山内
仲々盛会で大変面白い駅までぶらぶら歩いて笠 三井と帰る略。
(筆者注 ①野田高梧②沢村勉)
きっかけは、前年五月小津安二郎が鎌倉に居を定めたことによる。横須賀線の電車の中などで、東和映画の川喜多氏や朝日のQ氏こと津村秀夫などが乗り合せ、地元鎌倉で一杯やろうとなったにちがいない。
幹事長格は津村氏で、前述の小津、川喜多に加えて、野田高梧、田中絹代、岡村文子あたりが発起人になった。
二十八年と言えば、十一月に小津の最高傑作「東京物語」が出た年だ。九月には「君の名は」が封切られて空前のヒットとなった。松竹にとっては最高の年だった。
同じまちにいても、なかなか交流はないもので、すぐまたやろうという話になった。映画界のトップクラスがこんなに顔を揃えるのは、さすが鎌倉だ。時にはゲストも加わったりで、人数もふえ、賑やかな会になった。映画がそれだけ力のあった時代だったと言える。何時まで続いたかはっきり覚えてないが、一九八一年の写真があるからその頃が最後のように思う。折々の写真を見ながら、懐かしい、映画が華やかだった頃を振り返ってみる。 |
|
| |
|
 |